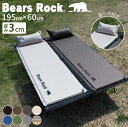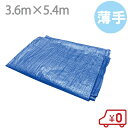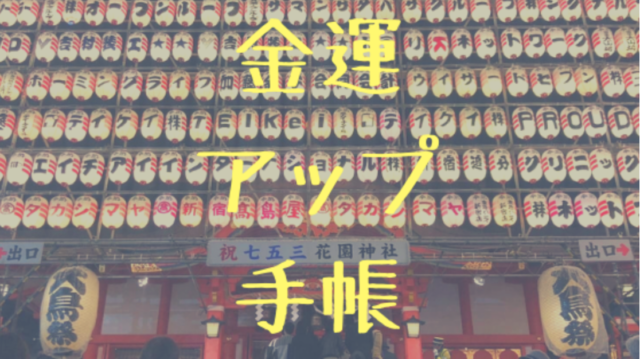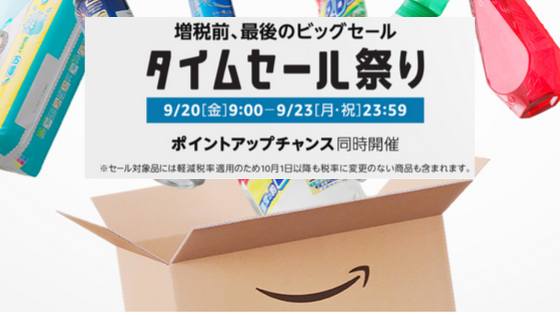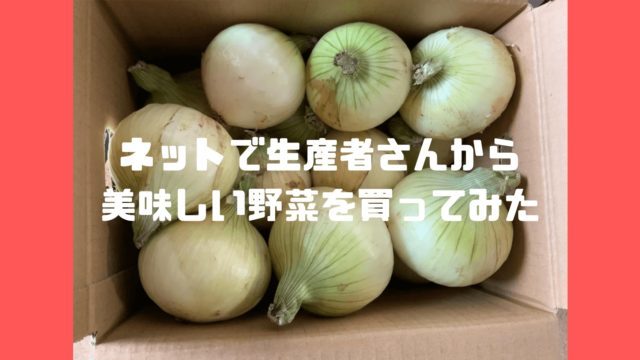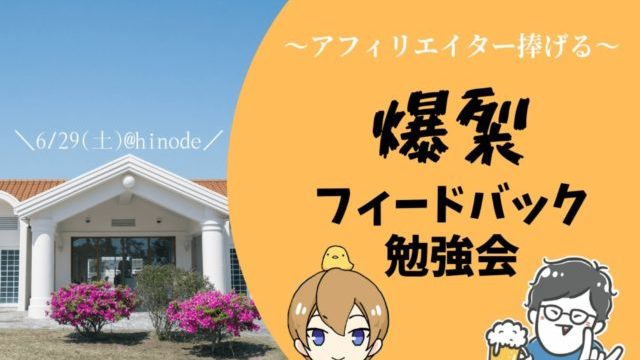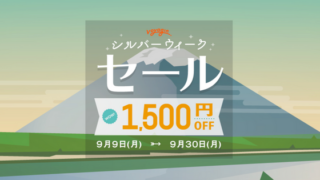会社の防災担当になったけど何から調べていいかわからない!
突然の災害で被災してしまった!
被災はしていないけれど備蓄はしていない!!
中小企業や小規模事業所、フリーランスやベンチャー企業などで防災対策は何をすべきかわからないですよね。
私も以前、突然会社の防災担当になって調べた時に、なかなかまとまっているページがなくて苦労しました…。
その時に参考にいした各行政や条例の出典リンクを含めた備蓄品のまとめをシェアします。
条例や法律によって内容が様々なので、ご自身の管轄の消防署や自治体のルールなども念のため各自でご確認ください。
細かいことはどうでもいいから何が必要か知りたい!という方は目次から【企業備蓄リスト】へ一気に飛んでください。
簡易版やご家庭用はこちらの記事からもみられます。
【厳選】家庭用おすすめ防災グッズまとめ 地震・大雨・台風災害備蓄チェックリスト
この記事はこんなあなたにおすすめ
- 中小企業や小規模事業所で防災対策は何をすべきかわからない!
- 一体どこを調べればいいのか?
- 防災備蓄の必要性を感じているがよくわからない
目次
- 1 1.企業防災とは何か?
- 2 2:企業防災の義務関係(※参考資料1)
- 3 参考となる資料のリスト
- 4 各種義務関係の条項(条文の関係箇所抜粋)
- 4.1 ②東京都帰宅困難者対策条例(2013年施行)
- 4.2 ③東京都震災対策条例(平成十二年東京都条例第二百二号)第十条(事業所防災計画の作成)
- 4.3 ④消防法
- 4.4 ⑤労働契約法
- 4.5 ⑥大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン(2015年施行)
- 4.6 ⑦港区防災マニュアル
- 4.7 ⑧東京都防災ガイドブック
- 4.8 (※参考資料2)港区事業所向け防災計画
- 4.9 (※参考資料3)株式会社〇〇消防計画目次
- 4.10 (参考資料4)東京防災
- 4.11 (参考資料5)中小企業の防災・事業継続の手引き
- 4.12 (参考資料6)官公庁及び地方公共団体等が発行している事業継続計画に関する Webサイトリスト
- 4.13 (参考資料7)中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」
- 5 【企業備蓄リスト】12人3日分チェックシート(参考)
- 6 まとめ
1.企業防災とは何か?

内閣府の定義
企業防災とは何か?
- 企業防災には、地震などによる災害被害を最小化する「防災」の観点からアプローチする場合と、災害時の企業活動の維持または早期回復を目指す「事業継続」の観点からアプローチする場合があります。
両者は互いに密接に関わり合い、共通した要素も多く存在することから、双方ともに推進すべきものですが、説明の便宜上、区分しています。「防災」
- 企業は、従業員や顧客の安全を第一に防災活動に取り組まなければなりません。また、地域の一員として、被害の軽減及び災害復旧・復興に貢献することが求められています。
「企業継続」
- 企業は、災害や事故で被害を受けても、取引先等の利害関係者から、重要な業務が中断しないこと、中断しても短い期間で再開することが望まれています。
出所:企業防災のページ(内閣府防災担当)
中小企業庁の説明
-
企業防災の促進
企業は、災害時の企業の果たす役割(生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・地域との共生)を十分に認識し、各企業において災害時に重要業務を継続するための事業継続計画(BCP)を策定するよう努めるとともに、防災体制の整備、防災訓練、事業所の耐震化、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し等を実施するなどの防災活動の推進に努めるものとする。
出所:中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/download/level_d/bcpent_01.pdf
2:企業防災の義務関係(※参考資料1)
| 出所名 | 義務区分 | 主な義務 |
| ①企業防災のページ
(内閣府防災担当) |
責務
しなければならない |
企業は、従業員や顧客の安全を第一に防災活動に取り組まなければなりません。 |
| ②東京都帰宅困難者対策条例 | 努力義務
努めなければならない |
・従業者、施設及び設備の安全性の確保
・帰宅困難者対策 ・従業者およびその家族など緊急を要するものとの連絡手段の確保 ・避難する場所の確認と徒歩での帰宅経路の確認 ・安全に帰宅させる方針を事業所防災計画に明記 ・上記事業所防災計画の従業者への周知 |
| ③東京都震災対策条例 | 義務
しなければいけない |
事業所防災計画を作成しなければならない |
| ④消防法 | − | ※企は従業員50人以下のため対象外 |
| ⑤労働契約法 | 推奨
するものとする |
使用者は労働者の生命の安全を守る配慮をするものとする |
| ⑥大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン | 自主的に遵守することが推奨されるルール、指針 | 企業等における施設内待機の計画策定と従業員等への周知、など |
| ⑦港区防災マニュアル | 推奨
事業所が必ずやる対策 |
1.事業所建物の耐震診断、耐震補強
2.地震対策組織の整備 3.BCP(事業継続計画)等文書類の整備 4.通信・連絡体制の整備 5.安否確認の手順と方法 6.備蓄(食糧、救命・救急用資器材など) 7.休日・夜間を含む社員参集方法の確立 防災訓練の実施 8.避難、退社計画の策定 9.帰宅困難者対策の策定(一斉帰宅の防止) 10.什器・備品の耐震対策 11.二次災害の防止策の実施(危険物等の管理) |
| ⑧東京都防災ガイドブック | 推奨
したほうがいい |
家族の安否情報共有システムについての備え |
上記資料の主な記述内容まとめ ※義務=◎、推奨=◯
| 記述内容 | ①企業防災のページ | ②東京都帰宅困難者対策条例 | ③東京都震災対策条例 | ④消防法 | ⑤ 労働契約法 | ⑥大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン | ⑦港区防災マニュアル | ⑧東京都防災ガイドブック |
| 従業者の安全の確保 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | |||
| 事業所建物の耐震診断、耐震補強 | ◯ | ◯ | ◎ | |||||
| 地震対策組織の整備 | ◎ | |||||||
| BCP(事業継続計画)等文書類の整備 | ◯ | ◯ | ◎ | |||||
| 通信・連絡体制の整備 /安否確認の手順と方法 | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | |||
| 備蓄(食糧、救命・救急用資器材など) | ◯ | ◎ | ||||||
| 休日・夜間を含む社員参集方法の確立 | ◎ | |||||||
| 防災訓練の実施 | ◯ | ◎ | ||||||
| 避難、退社計画の策定 | ◯ | ◯ | ◎ | |||||
| 帰宅困難者対策の策定(一斉帰宅の防止) | ◯ | ◯ | ◎ | |||||
| 什器・備品の耐震対策 | ◯ | ◎ | ||||||
| 二次災害の防止策の実施(危険物等の管理) | ◯ | ◎ | ||||||
| 情報提供、防災計画の周知 | ◯ | ◯ | ◯ |
参考となる資料のリスト
(※参考資料1)
企業に課される義務関係(まとめ)
①内閣府
企業は、従業員や顧客の安全を第一に防災活動に取り組まなければなりません。
②東京都帰宅困難者対策条例
- 施設及び設備の安全性の確保
- 帰宅困難者対策
- 従業者およびその家族など緊急を要するものとの連絡手段の確保
- 避難する場所の確認と徒歩での帰宅経路の確認
- 安全に帰宅させる方針を事業所防災計画に明記
- 上記事業所防災計画の従業者への周知
③東京都震災対策条例
事業所防災計画を作成しなければならない
④消防法
従業員50人以下の企業は対象外
⑤労働契約法
使用者は労働者の生命の安全を守る配慮をするものとする
⑥大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン
◇企業等における対応
[平常時]
1.企業等における施設内待機の計画策定と従業員等への周知
2.企業等における施設内待機のための備蓄(参考資料2)
・備蓄品の保管場所の分散や従業員等への配布を検討する
・備蓄量の目安は3日分とするが、3日分以上の備蓄についても検討する
・外部の帰宅困難者のために、例えば、10%程度の量を余分に備蓄する
3.平時からの施設の安全確保・オフィスの家具類の転倒等の防止や、ガラス飛散の防止対策等に努める ・地震発生時の建物内の安全点検のためのチェックシート※1を作成する※1 チェックシートは「大規模地震発生直後における施設管理者等による建物の緊急点検に係る指針」(平成27年2月内閣府(防災担当))を参考とすると良い。(参考資料3)
4.従業員等への安否確認手段、従業員等と家族との安否確認手段の確保
5.帰宅時間が集中しないような帰宅ルールの設定
6.年1 回以上の訓練等による定期的な手順の確認
[発災時]
1.従業員等の施設内待機
・従業員等が安全点検のチェックシートにより施設の安全を確認する・災害関連情報等を入手し、周辺の火災状況等を確認し、従業員等を施設
内又は他の安全な場所に待機させる・来所者についても、従業員等に準じて、施設内又は他の安全な場所で待
機させるようにする
2.施設内に待機できない場合の対応
・建物や周辺が安全でない場合、一時滞在施設※2等へ従業員等を案内又は 誘導する
[混乱収拾時以降]]
1.帰宅開始の判断
・行政や関係機関からの情報等により、安全に帰宅できることを確認する ・確認後、あらかじめ定めたルール等に基づいて従業員等を帰宅させる
⑦港区防災マニュアル
事業所が必ずやる対策
- 事業所建物の耐震診断、耐震補強
- 地震対策組織の整備
- BCP(事業継続計画)等文書類の整備
- 通信・連絡体制の整備
- 安否確認の手順と方法
- 備蓄(食糧、救命・救急用資器材など)
- 休日・夜間を含む社員参集方法の確立
- 防災訓練の実施
- 避難、退社計画の策定
- 帰宅困難者対策の策定(一斉帰宅の防止)
- 什器・備品の耐震対策
- 二次災害の防止策の実施(危険物等の管理)
⑧東京都防災ガイドブック
事所業では、従業員が施設内に待機するために、3日分の飲料水・食料等を備蓄した り、 駅や集客施設等でも、利用者を保護するなどの取組をお願いします。(中略)事業者においては、災害時の従業員等の一斉帰宅の抑制、安否確認のための連絡手段の確保、3日分の備蓄、帰宅ルールなどを、事業所防災計画に規定し、首都直下地震等に備えるようにしましょう。
各種義務関係の条項(条文の関係箇所抜粋)
②東京都帰宅困難者対策条例(2013年施行)
企業に対して、防災対策・防災備蓄・安否確認体制の構築を「努力義務」としている
出所:https://sonaeru.jp/bcp/basis/intro/c-14/
(事業者の責務)
第四条 事業者は、その社会的責任を認識して、従業者の安全並びに管理する施設及び設備の安全性の確保に努めるとともに、大規模災害の発生時において、都、区市町村、他の事業者その他関係機関と連携し、帰宅困難者対策に取り組むよう努めなければならない。2 事業者は、あらかじめ、大規模災害の発生時における従業者との連絡手段の確保に努めるとともに、家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段の確保、待機し、又は避難する場所の確認、徒歩による帰宅経路の確認その他必要な準備を行うことを従業者へ周知するよう努めなければならない。
3 事業者は、管理する施設の周辺において多数の帰宅困難者が生じることによる混乱及び事故の発生等を防止するため、都、区市町村、他の事業者その他関係機関及び当該施設の周辺地域における住民との連携及び協力に努めなければならない。
4 事業者は、あらかじめ、大規模災害の発生時における従業者の施設内での待機に係る方針、安全に帰宅させるための方針等について、東京都震災対策条例(平成十二年東京都条例第二百二号)第十条に規定する事業所防災計画その他の事業者が防災のために作成する計画において明らかにし、当該計画を従業者へ周知するとともに、定期的に内容の確認及び改善に努めなければならない。
(従業者の一斉帰宅抑制)
第七条 事業者は、大規模災害の発生時において、管理する事業所その他の施設及び設備の安全性並びに周辺の状況を確認の上、従業者に対する当該施設内での待機の指示その他の必要な措置を講じることにより、従業者が一斉に帰宅することの抑制に努めなければならない。
2 事業者は、前項に規定する従業者の施設内での待機を維持するために、知事が別に定めるところにより、従業者の三日分の飲料水、食糧その他災害時における必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。
出所:http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1014283001.html
③東京都震災対策条例(平成十二年東京都条例第二百二号)第十条(事業所防災計画の作成)
第十条 事業者は、その事業活動に関して震災を防止するため、都及び区市町村が作成する地域防災計画を基準として、事業所単位の防災計画(以下「事業所防災計画」という。)を作成しなければならない。
出所:http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1010173001.html#j10
④消防法
防火管理者が必要な防火対象物等共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)の防火対象物を「非特定防火対象物」といい、防火対象物全体の収容人員が50人以上のものが該当します
出所:東京消防庁
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/office_adv/jissen/h28_1.pdf
出所:東京都消防設備協同組合
http://tfs.or.jp/bouka-kanri-01/toukatsu-bouka-bousa-kanri-02.html
※消防法 全文https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC1000000186
⑤労働契約法
第5条(労働者の安全への配慮)使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
出所:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/13.pdf
⑥大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン(2015年施行)
第2章2 災害発生時の対応フロー・BCPの策定
防災対策や備蓄用品を災害発生時に生かすために運用フローを定めておくことが重要
- 備蓄用品の保管場所の把握と管理
- どの規模の災害が生じた際に、誰の権限でどの備蓄用品をどのくらい配布するのか
- どの取引先へいつ誰が連絡して業務再開の優先順位はどうするのか
出所:内閣府防災担当 大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン
http://www.bousai.go.jp/jishin/kitakukonnan/pdf/kitakukonnan_guideline.pdf
⑦港区防災マニュアル
必ずやる対策
- 地震対策組織の整備
- BCP(事業継続計画)等文書類の整備
- 通信・連絡体制の整備
- 安否確認の手順と方法
- 備蓄(食糧、救命・救急用資器材など)
- 休日・夜間を含む社員参集方法の確立
- 防災訓練の実施
- 避難、退社計画の策定
- 帰宅困難者対策の策定(一斉帰宅の防止)
- 什器・備品の耐震対策
- 二次災害の防止策の実施(危険物等の管理)
- 情報提供やったほうがいい対策
-
- 防災教育・訓練(特殊なもの)の実施
- 救命、救急用資器材の備蓄、調達(特殊なもの)
- 地域協力(社屋の開放、備蓄食糧の支援など)
-
出所:港区防災マニュアル
https://www.city.minato.tokyo.jp/bousai/syokubabousai/documents/jigyousyobousaimanyuaru.pdf
⑧東京都防災ガイドブック
「東京都帰宅困難者対策条例」が、平成25年4月より施行されました。 事所業では、従業員が施設内に待機するために、3日分の飲料水・食料等を備蓄したり、駅や集客施設等でも、利用者を保護するなどの取組をお願いします。(中略)事業者においては、災害時の従業員等の一斉帰宅の抑制、安否確認のための連絡手段の確保、3日分の備蓄、帰宅ルールなどを、事業所防災計画に規定し、首都直下地震等に備えるようにしましょう。
1) 家族等との安否確認手段
発災時、通常の電話は輻輳するためつながりにくくなります。日頃から家族等との安否確認手段を複数確保しておきましょう。
【代表的な安否確認ツールの紹介】
- 従業員・家族の安否確認システムについて
- 電子メール:GmailやyahooメールなどWeb上で扱える
- ソーシャルメディア:TwitterやFacebookなど
- インターネット回線を用いた連絡手段:skypeやLINEなど
- NTTの災害伝言ダイヤル「171」
- 携帯電話会社が提供している災害用伝言サービス
※定期的な防災訓練時などに、実際に災害伝言ダイヤルやソーシャルメディアを用いて、従業員が家族に連絡をする練習をさせるなどして、使い方を学ばせておくことが重要
出所:東京都防災ガイドブック
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/common/guidbook_pocketguide/2019guid_j.pdf
(※参考資料2)港区事業所向け防災計画
https://www.city.minato.tokyo.jp/chiikikeikakutan/chibouh24.html
参考テンプレートhttps://www.city.minato.tokyo.jp/bousai/syokubabousai/…/bcptenpure-tword.doc
1.事業計画の目的、適用範囲等(目的、適応範囲、災害の想定)
2.再開・復旧に関する基本方針
3.重要業務と復旧目標
4.災害発生前の対策(設備・備品等の整備計画)
5.災害発生時の対策(担当者や行動基準、初動・緊急時の対応フロー)
6.災害発生後の対策(被害状況の確認・取引先への連絡)
7.防災教育及び訓練
(※参考資料3)株式会社〇〇消防計画目次
1.目的と適用範囲
2.管理権原者の責任及び防火管理者の業務
3.火災予防状の自主検査
4.防火対象物及び消防用設備の点検
5.従業員の守るべき事項
6.放火防止対策
7.工事等における安全対策
8.放火・防災教育
9.訓練
10.消防機関への連絡、報告
11.放火管理業務の一部委託(有・無)
12.自衛消防組織
13.事業所自衛消防隊の編成及び任務等
14.震災対策
15.大規模テロ等に伴う災害対策
16.大雨・強風対策
17.受傷事故等にかかる自衛消防対策
18.その他防火管理上必要な事項
- 19.避難経路図の掲示
- 別表1.自主検査票(日常)
- 別表2.自主検査票(定期)
- 別表3.自衛消防隊訓練実施計画記録書
- 別表4.オフィス家具類の転倒・落下・移動防止対策チェックリスト
- 別表5.一斉帰宅抑制における従業員等のための備蓄(例)
- 別表6.震災時における時差退社計画(例)
- 別表7.施設の安全点検のためのチェックリスト(例)
- 別表8.防火・防災の手引き(新入社員用)
- 別表9.防火・防災の手引き
(参考資料4)東京防災
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1002147/index.html
会社の災害対策
- マニュアル・ルールを作る
会社では防災担当を決め、防災会議を開いて、避難方法や避難場所、連絡網のフローなどのルールをつくりましょう。発災後、帰宅のタイミングは原則72時間以上ですから、帰宅困難者が出た場合の資材整備も必要です。人事異動などで職場の環境が変わった場合には、マニュアルを再確認するようにします。- 防火防災訓練を行う
- 帰宅困難に備える
(例)鹿島建設株式会社
在籍者の3日分の備蓄品をシステムを利用して一元管理するとともに、社員それぞれが震災発生時の役割を果たせるよう年4回訓練を実施
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/146/ichiran.pdf
(参考資料5)中小企業の防災・事業継続の手引き
財団法人埼玉県中小企業振興公社/埼玉県産業労働部産業支援課
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/keizoku/pdf/bcp-manual.pdf
「防災・事業継続計画」の作成・実施
「防災・事業継続計画」とは、地震などの災害や事故・事件など が起きた場合に、企業が、従来の防災対策に加え、中核事業の継続・早期復旧を 図るために平常時に行うべき活動並びに緊急時(災害時)の対応方法、手段など を事前に取り決めておく計画です。
1.基本方針の策定(詳細の内容や文書化は後回しにしても構いません)
2.対象とする災害・事故の選定
3.現状把握と計画策定
-1 中核事業の抽出と目標復旧期間の設定
-2 重要業務の要素(ボトルネック資源)の抽出
-3 「事前対策実施計画」と「緊急時対応・復旧計画」
4.計画の実施と運用
-1 組織体制と緊急連絡先
-2 対応マニュアル・チェックリストの作成
-3 教育・訓練の実施
5 点検・是正
6 経営層による見直し
(参考資料6)官公庁及び地方公共団体等が発行している事業継続計画に関する Webサイトリスト
○内閣府:「事業継続ガイドライン第一版 解説書」
http://www.bousai.go.jp/kigyo-machi/jigyou-keizoku/guideline01_und.pdf
同:「事業継続計画(BCP)の文書構成モデル例 第一版」
http://www.udri.net/portal/kigyoubousai/model-nol-1.pdf
○中小企業庁:中小企業BCP策定運用指針
http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/
○徳島県企業防災ガイドライン (企業BCPについてわかりやすい)
http://www1.pref.tokushima.jp/005/01/kibou/
○静岡県事業継続計画モデルプラン (企業BCP詳細)
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-510/bcp/index.html
○国土交通省関東地方整備局
http://www.ktr.mlit.go.jp/bousai/index00000046.html
★平常時における事前の防災対策に対する支援制度を紹介します。
○中小企業組合等活路開拓事業 ・中小企業が組合等を中心に共同して調査研究、将来ビジョンの策定及び
その成果を具体的に実現化し、新たな活路を見出すために行う事業 ・補助金額は、総事業費の10分の6以内であって12,118千円が限度 ・全国中小企業団体中央会 http://www.chuokai.or.jp/josei/josei.htm
・窓 口:各都道府県の中小企業団体中央会
・対 象:協同組合が対象
(参考資料7)中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」
https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/download/level_d/bcpent_01.pdf
【様式 1】 BCPの基本方針
1.目的
- 基本方針
- 重要商品
【様式 2】 被害想定
【様式 3】 重要商品提供のための対策
- 事前対策の検討
【様式 4】 緊急時の体制
- 緊急時の統括責任者
【様式 5】 BCPの運用
- BCPの定着
- BCPの見直し
【企業備蓄リスト】12人3日分チェックシート(参考)

以上の各行政などの方針に則り、社員6人、来客6人、合計12人の3日分で必要な企業備蓄をピックアップしてみました。
意外と時間がかかったので参考にしていただいて時間短縮になれば幸いです。
Amazonで手配できるもので見積もった結果、調達予定額は約15万円ほど。
詳細は下記リンクより詳しくみれます。
【厳選】家庭用おすすめ防災グッズまとめ 地震・大雨・台風災害備蓄チェックリスト
他にスプレッドシートを作成し保管や備蓄の点検に活用。
|
|
アイテム |
数量目安 |
耐用年数 |
|
A.避難用品 |
|||
|
A-1 |
懐中電灯 |
5個(部屋数分) |
長期利用可能 |
|
A-2 |
LEDランタン |
1個(在庫あり) |
長期利用可能 |
|
A-3 |
救急セット(包帯、絆創膏、消毒液など) |
1セット |
3年 |
|
A-4 |
胃腸薬 |
1箱48包 |
3年 |
|
A-5 |
解熱剤 |
1箱60錠 |
3年 |
|
A-6 |
乾電池単3(20本セット) |
20本 |
3年 |
|
A-7 |
乾電池単4(16本セット) |
27本 |
3年 |
|
A-8 |
寝袋型アルミシート |
12人×1枚 |
5年 |
|
A-9 |
ろうそく(太・6本セット) |
6個 |
10年 |
|
A-10 |
使い捨てカイロ(10枚セット) |
36枚(12人×1枚/日×3日) |
3年 |
|
A-11 |
マスク(60枚) |
1箱(60枚) |
長期利用可能 |
|
A-12 |
手回しソーラー充電ラジオ |
2個 |
長期利用可能 |
|
A-13 |
ヘルメット |
12個 |
長期利用可能 |
|
A-14 |
軍手(12組セット) |
12組 |
長期利用可能 |
|
A-15 |
レインコート(上着) |
12組 |
長期利用可能 |
|
A-17 |
ビニールシート |
2枚 |
長期利用可能 |
|
A-18 |
地図 |
1個(在庫あり) |
長期利用可能 |
|
A-19 |
ガムテープ |
1巻(在庫あり) |
3年 |
|
A-20 |
持出袋 |
確定予定 |
長期利用可能 |
|
B.滞在用品(水・食料など) |
|||
|
B-1 |
水(2l×12本) |
108l(12人×3l/日×3日) |
5年 |
|
B-2 |
アルファ化米(12食セット) |
36食分(12人×1食/日×3日) |
5年 |
3
|
B-3 |
長期保存用パン(24食セット) |
36食分(12人×1食/ 日×3日) |
5年 |
|
B-4 |
長期保存用ラーメン(3種12缶) |
36食分(12人×1食/ 日×3日) |
5年 |
|
B-5 |
ビスコ(30個入り×2缶) |
60個(12人×3日) |
5年 |
|
C.滞在用品(調理) |
|||
|
C-1 |
携帯用ガスコンロ |
1台 |
長期利用可能 |
|
C-2 |
カセットガス |
3本 |
7年 |
|
C-3 |
チャッカマン |
2個 |
長期利用可能 |
|
C-4 |
紙皿(深さ13cm、350cm、100枚セット) |
100枚×2 |
長期利用可能 |
|
C-5 |
紙コップ(100枚セット) |
100枚×2 |
長期利用可能 |
|
C-7 |
ラップ |
1本 |
長期保存可能 |
|
D.滞在用品(衛生用品) |
|||
|
D-01 |
ウォーターバッグ(10l) |
2個 |
長期利用可能 |
|
D-02 |
ウォータータンク(22l) |
2個 |
長期利用可能 |
|
D-3 |
簡易トイレ(排泄物用凝固剤) |
最低5回×3日×12人 =180回分 |
7年前後 |
|
D-4 |
簡易トイレ(排泄物袋) |
180枚 |
長期利用可能 |
|
D-5 |
簡易トイレ(防臭機能付排泄物袋一時保管 袋) |
60枚 |
長期利用可能 |
|
D-6 |
生理用品(66枚) |
1セット |
長期利用可能 |
|
D-7 |
タオル(10枚セット) |
10枚セット×2 |
長期利用可能 |
|
D-9 |
トイレットペーパー |
常備 |
長期利用可能 |
|
D-10 |
ティッシュ |
常備 |
長期利用可能 |
|
D-11 |
ウェットティッシュ(360枚セット) |
360枚セット |
3年 |
|
D-12 |
歯ブラシ(100個、歯磨き粉付き) |
100個 |
3年 |
|
D-14 |
体拭きシート(30枚セット) |
60枚 |
3年 |
|
D-15 |
除菌アルコール |
1本 |
3年 |
|
D-16 |
ドライシャンプー |
1本(在庫あり) |
3年 |
|
D-17 |
ポリ袋 |
在庫あり |
長期利用可能 |
|
D-18 |
ラテックス手袋(100枚セット) |
1個 |
長期利用可能 |
どんなものがあるのか細かく見ていきましょう!
- 長期保存の水
長期保存用の水なら安心です。 - 長期保存のパン
- 長期保存の米
- 長期保存のお菓子
災害時はなかなか食料が手に入らないこともあるので何パターンか揃えとくと安心です。
- 長期保存の野菜ジュース
最近では長期保存用の野菜ジュースもあるので栄養面も考えるとあると安心です。 - ラップ
食料の保存用だけでなくお皿に敷いて使えば断水の時も洗い物いらずです。
また水漏れしてしまった場合の応急処置やトイレの逆流対策にも使えます。 - 紙皿
こちらも断水時などに - 紙コップ
- 使い捨てスプーンなど
- ラテックス手袋
こちらも断水した時などに手洗いの必要がなく食料を取り分けたり調理することができます。
応急処置用品1択
いざという時にあると安心なのがファーストエイド、応急処置用品です。
アウトドア・登山にも使えるので1つあると便利です。
- ファーストエイド
避難用品15選
いざ避難が必要になった時に必要なのが身を守るものです。
避難最中に必要なヘルメットや軍手、雨具などを持っておくと安心です。
また、避難所では物資が足りないこともあるので持っていけるものは持参するといざという時に困りません。
- ヘルメット
- 軍手
- 雨具
- 防水スマホケース
- 常備薬
- 災害用マップ
- 避難用マット
- 充電器
- たこ足配線
- イヤフォン
- 耳栓
- マスク
- アイマスク
- 簡易スリッパ・クロックスなど
- 防水持ち出し袋
こちらも細かく見てみましょう。
- ヘルメット
- 軍手
- 雨具
雨具はしまっておくだけではもったいないので、できればアウトドアグッズなどしっかりしたものがあると日常使いもできて便利です。 - 防水スマホケース
- 常備薬
避難所では薬も何があるかわかりません。特に大人数で避難する場合などはストレスから頭痛や腹痛を起こしてしまうこともあると思うので常備薬は持っていた方がいいです。 - 災害用マップ(各自治体や自分の地域のハザードマップ)
- 避難用マット
- 充電器
- たこ足配線
避難所で電気が通っている場合はプラグの取り合いになるのであると便利です。 - イヤフォン
- 耳栓
- マスク
- アイマスク
- 簡易スリッパ・クロックスなど
- 防水持ち出し袋
滞在用品13選
避難するまでもないけれど長期で自宅待機をしなければならない場合。
電気が切れる、水道・ガスが使えないことを想定すると色々必要になってきます。
- ソーラー充電式ラジオ
- 懐中電灯やランタン
- 電池
- ろうそく
- チャッカマン
- ブルーシート(ガラスが割れたり水漏れなどの対策)
- 養生テープ
- ゴミ袋
- 保温グッズ
- ホッカイロ
- 発電機
- カセットコンロ
- ガス
- 暖房器具
- 扇風機など
詳しく見ていきましょう。
- ソーラー充電式ラジオ
- 懐中電灯やランタン
- 電池
- ろうそく
長時間持つろうそくがおすすめですが、懐中電灯などを持っていて予備に持っておきたい場合はアロマキャンドルもおすすめです。
通常時は部屋のインテリアになりますしリラックスする香りを選べばストレスの緩和もできます。またビンなどに入っていてそのまま火をつけるだけなものも多いので安全面も安心です。 - チャッカマン
- ブルーシート(ガラスが割れたり水漏れなどの対策)
- 養生テープ
- ゴミ袋
- 保温グッズ
避難所などの生活音はストレスになるようなので、音がカサカサならないアルミの防寒グッズが高評価でした。 - ホッカイロ
- 発電機
- カセットコンロ
- ガス
- 暖房器具
- 扇風機など
- 簡易トイレ・トイレ凝固剤
- ゴミ袋
- オムツ・生理用品
- 体拭きシート(人間・ペット用もあり)
- 水のいらないシャンプー
- 速乾タオル
- マスク
- ウォータータンク
- 歯磨きシート
日本の避難所はプライバシーが配慮されていないところが多いので生理用品やプライバシーのための毛布などもあった方が良いでしょう。
避難所での性犯罪の話もあるようなので
- 子供を一人で歩かせないようにする
- 女性も単独行動を避ける
方が良さそうです。
【家庭用おすすめ防災備蓄グッズチェックリスト】地震・大雨・台風に備えあれば患なし
まとめ
調べているうちに過去の災害の資料なども拝見し、災害は本当にいつ訪れるかわからないので従業員や家族を守るための備蓄の必要性を感じました。
お役に立てれば幸いです。
では、また🌟