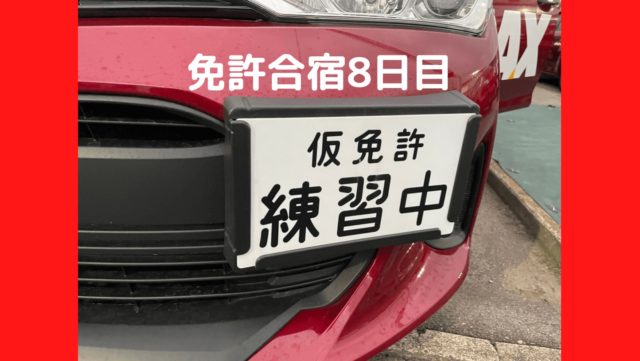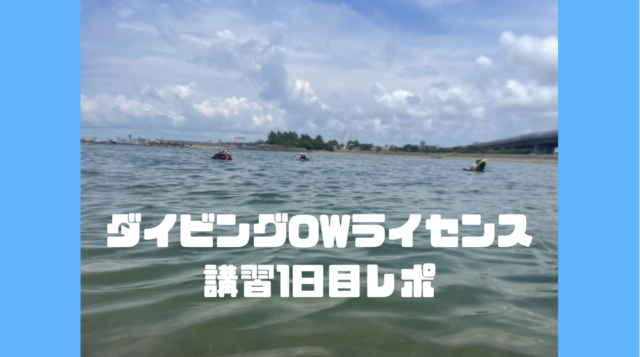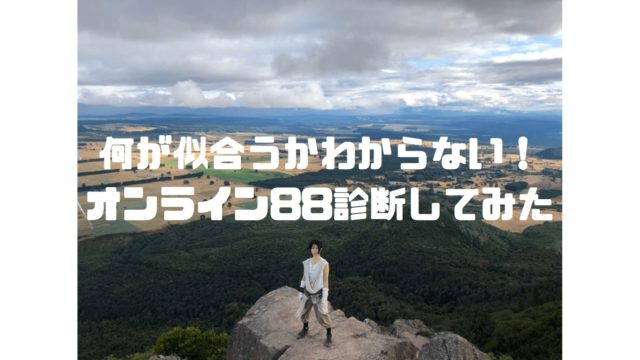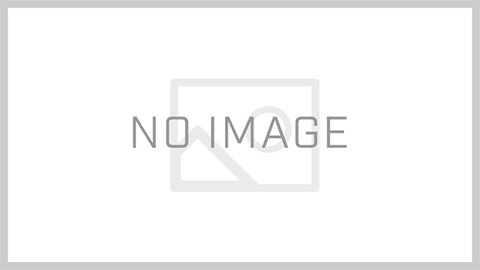「仮免検定ってどんなことをするの?」
「終わった後はどうなるの?」
そんな疑問はありませんか?
結論から言うと、仮免検定は、車の運転技能の実技と、筆記の2つ合格する必須です!
合宿の場合合格するとすぐに仮免が渡され、そのまま第二段階の講義に突入します。
逆に合格しないと次の予定も決まりませんし、補修をして翌日以降に再試験を受けなければなりません。
目次
【合宿免許】長野県MAXドライビングスクール千曲レポ(8日目)

【合宿免許】長野県MAXドライビングスクール千曲レポ(8日目)
- 9:10 仮免検定
- 10:45 筆記試験
- ランチ
- 13:30 AT路上(技能)
- 14:30 AT路上(技能)
- 15:30 学科①「車に働く自然の力と運転」
- 16:30 学科②「死角と運転」
- 17:30 AT路上(技能)
- 18:30 学科③「特徴的な事故と事故の悲惨さ」
- 19:30 学科④「乗車と積載」
朝はなぜか片目が痛くてコンタクトが入らなかったり、毎日快晴だったのに曇天でちょっと気持ちがナーバスになりそうでしたが、逆に開き直れました。
メガネで運転をしたことがなかったので、なんとか目が落ち着いて新しいコンタクトを再度開けたら入れられてよかったです。
9:10 仮免検定(実技)
担当は初めての教官でしたが、説明のときに優しかったので変な緊張はしませんでした。
「検定の後に、感じが悪かったって感想を書かれることがありますが、検定中はルート以外は話せない決まりなので怒ってるとかではありませんからね」
的なことをおっしゃっていました(笑)
「やめたほうがいいんじゃないか」と書かれたことがあるらしいです(笑)
検定は3人で1組になって、1、2、3の番号順に行われます。
1の番号の試験のときに2の人が後ろに同乗、2の人のときに3の人が同乗、という形で行われます。
待ち時間は説明を受けた教室で待機。
私は2番だったので、前の人の運転を見学できました(しめしめ)
昨日も一昨日も同じ時間に運転の授業があったので、運転する時間には慣れてきていました。
この日は曇っていたので、眩しさもなく快適な条件。
2人目の検査のはずなのにずっとハンドアマークがついていて、なぜか後ろの荷物を入れるところがハンドアでした。
みんなでバタバタドアの開け閉めしていたら緊張がほぐれました。
- 交差点を直進中に左から来た右折車待ってしまった
10:45 筆記試験

終わった人から教室で待機だったので、筆記試験の勉強をしました。
間違えたところなどを練習問題の「楽勝問題」を使って復習。
ドキドキ。
試験時間は60分で、問題は50問。
1問2点で、100点満点の90点以上で合格です。
多分最低でも多分2問は間違えました。
- 大型バス専用道路は左折の時に入ってはいけない。
→一番左が大型バスレーンの場合、入らないと左折できない。 - 発進するときは、合図を出して前後左右をバックミラーなどで確認する。→前後左右を確認してから、合図を出して、目視で再度確認が正解?
- 「みんなを守る 安全運転」を全部読む
- 普段からちょっとずつ練習問題を解いて少しずつ問題の言い回しに慣れる
- 教習所の「楽勝問題」やアプリでひたすら問題を解いて間違えたところをチェック
ランチ

今日のランチは魚のフライ。
お腹が弱いマンなので揚げ物怖い。
合格発表
12:20に集合して合格発表です。
この日の受験者は6名。
全員合格でした!!
午後以降のスケジュールが配られると、1日遅れで試験だったので延泊になってなかった!!
ありがたや!!
途中で遅れてしまっても、スケジュール次第では取り戻せることもあるみたいです!!
遅れても諦めないで!!
焦って動揺するよりも着実に技術を身につけたほうが試験に落ちなくて結局早く進める!
頑張ろう。
13:30 AT路上(技能)
早速初めての路上。
つまり公道を走ります。
こわ。
初めての行動は穏やかな女性の先生で安心。
14:30 AT路上(技能)

路上かと思いきや場内で危険実験の時間。
急ブレーキの練習をしてABSを体感したり、道路の真ん中を走ってギリギリで障害物を避けて、危険がどういうことなのか体感します。
15:30 学科①「車に働く自然の力と運転」
車のコントロールにも限界があるので、無理のない運転をしましょうという項目。
- 慣性の法則…運動している物体は、力を加えなければ動き続けようとする
- 摩擦力…タイヤと路面との間にタイヤの運動を妨げる力
- グリップ…タイヤが摩擦力で路面を掴むようにすること
- 慣性力>摩擦力だと目標地点で止まれない
- 摩擦係数…2つの物の間の「滑りにくさ」を表す数値
(乾いた舗装道路:0.8 濡れた未舗装道路:0.4 雪道:0.2) - 車の停止距離=空走距離+制動距離
- 遠心力はカーブの半径、速度、重さできまる
下り坂でフットブレーキを多用すると、フェード現象やベーバーロック現象で制御ができなくなることも。
- フェード現象…ブレーキ装置が加熱して摩擦力が弱くなって危機が弱くなる現象
- ベーバーロック現象…ブレーキ装置が加熱してブレーキ液の中に気泡ができて、ブレーキペダルを踏んでも十分に油圧が伝わらず、ブレーキが効かなくなる現象。
前車との車間距離をしっかりと取りながら早めにスピードを緩めることが大事。
- 坂道では、下りの車が上りの車に道を譲る
- 退避場所があるときは、上り下りに関係なく待つ
- 崖側の車が安全な場所に停止して待つ
- 長い上り坂で遅いときは左に寄って徐行して道を譲る
免許が取れると自動的に原付も運転できるようになります。
二輪車の特性も学ぶ。
- 二輪車は、人車一体の重心(重力、遠心力、合力)
- 上り坂では重心を前に(立ち姿勢で腰を前に動かしたり上体を前に傾けたり)
- 下り坂では重心を前に(立ち姿勢で腰を引いたり上体を起こしたり)
MT二輪車の正しい乗り方
- ステップにつり踏まずを乗せて足の裏はほぼ水平
- 足先がまっすぐ前方向きで、タンクを両膝でしめる(ニーグリップ)
- 手首を下げ、ハンドルを前に押すような気持ちでグリップを軽く持つ
- 肩の力を抜いて、肘を僅かに曲げる
- 背筋を伸ばして、視線は前
体にあったマシンを選びましょう。
二輪車のブレーキ
- 車体を垂直にして、エンジンブレーキを効かせながら前後輪のブレーキを同時に
- 乾燥した路面では、前輪ブレーキ強め
- 滑りやすいときは後輪強め
授業で絶対に覚えるって言われたのはこちら。
二人乗りの禁止
- 規制標識のある道路
- 一般道路…大型・普通二輪免許を持っている期間が通算1年未満
- 高速…①20歳未満 ②上記通算3年未満
16:30 学科②「死角と運転」
危険には見えている顕在的な危険と、見えない死角などの潜在的危険があります。
- 交差点の右方向からくる車
- 交差点の左寄りを走行する二輪車
- 右折時に対向車線の影から出てくる二輪車
- 左折時の巻き込み事故
- 駐車場から道路に入るときの自転車や歩行者
いつでも止まれる速度80km/h10km/hでじわじわ進む
防衛的運転方法
- 安全空間(車間距離)の確保
- 危険を回避できる速度=徐行
- 安全な走行位置(右左折の寄せ、待つときはハンドルまっすぐ)
- 明確な運転行動のアピール(合図やポンピングブレーキ、ライト)
コミュニケーション
- パッシング(止まっている)…お先にどうぞ
- パッシング(速度落とさない)…先行くぜ
- 前照灯上向き…夜間の信号ない交差点で存在アピール
- 前照灯を消す…狭い道で対向車に道を譲る
- 左ウィンカー(一車線の道路で前の車が減速して左側に寄った)…追い越してください
- ハザードランプ(高速道路)…渋滞のお知らせ
- ハザードランプ…感謝、これからバック駐車する、路上停車する(減速しながら)
17:30 AT路上(技能)
初めての夜の運転。
眩惑(げんわく)…対向車のライトを見ると眩しくて一瞬見えなくなる
蒸発減少…対向車と自分の車のライトで歩行者などが見えなくなること
18:30 学科③「特徴的な事故と事故の悲惨さ」
若者の減少と車離れで交通事故件数と死傷者数は年々減少しているけれど、高齢者の事故は増えている!
事故の傾向
- 死者の割合は圧倒的に高齢者
- 事故の発生場所は交差点とその付近が最も多い
- カーブの事故件数は少ないが死亡事故率が高い
- 交差点は女性、カーブは男性が多い傾向
- 発生時間帯は通勤時間の8-10時、16-20時が多い
- 主な原因は安全不確認、脇見運転、漫然運転
19:30 学科④「乗車と積載」(ほぼ全部覚える)

後ほどまとめます。
まとめ

なんとか受かりました!!
緊張した!!
受かった瞬間から怒涛の第二段階!!
次の試験もすぐにあるので気は抜けません。
とりあえず、休息はしっかり取りながら、明日からも頑張ります!!
では、また明日☆